本記事はシリーズ「マクスウェル方程式で解析する電磁気学」の第2部です。第2部では電磁気学で初めの関門とも言える電磁ポテンシャルについてどのように取り扱われるのか解説していきます。電磁ポテンシャルはただの電磁場を表現するポテンシャルなのですが、どうもよく分からないまま登場して何の役に立つのか分からないまま退場した学生も少なくないはずです。
初回(前回)
次回
初めに
電磁ポテンシャルは電磁気学において重要な概念の一つです。ベクトル場を構成する情報源であるポテンシャルを導入することで電磁気学の解析がより容易になります。電磁気学においては、電荷や電流が発生することで電場や磁場が発生しますが、これらは電磁ポテンシャルを用いて表現することができます。
電磁ポテンシャルにはスカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルの2種類があります。スカラーポテンシャルは電荷によって発生する電場に対して用いられ、ベクトルポテンシャルは電流によって発生する磁場に対して用いられます。この電磁ポテンシャルによる恩恵は以下のような電磁場が一意に定まらない場合に大いに授かることになりましょう。
- 電荷分布が非局所的である場合:電荷が無限遠方まで広がっている場合には、電荷分布が一意に定まらず電場が一意に定まらなくなります。
- 磁場が時間的に変化している場合:ファラデーの電磁誘導の法則により磁場の時間変化によって電場が発生します。つまり磁場が時間的に変化している場合には電場も一意に定まらなくなります。
- 物質が磁性を持つ場合:磁性物質においては磁化により磁場が生じます。磁化は物質中の電子のスピンや軌道運動量に起因するため、物質によって磁場が異なり磁場が一意に定まらなくなります。
- 位置によって電場が異なる場合:電場は周囲の電荷分布によって決まります。しかし電荷分布が不均一な場合には、同じ位置でも周囲の電荷分布によって電場が異なり一意に定まらなくなります。
電磁ポテンシャルの導入
ベクトル量とスカラー量のポテンシャル
ベクトル解析学で言うポテンシャルとは、ベクトル場 $\boldsymbol{F}$ を形成するための情報源である。簡潔に言いすぎてしまったためあまりスッキリしない読者もいるかもしれないが、例えば重力や弾性力等の保存力によって伴うスカラーポテンシャル $U$ は高校生の読者にも馴染みがあるものだろう。
保存力 $\boldsymbol{F}$ はスカラーポテンシャル $U$ によって
$$\boldsymbol{F}=-\nabla U \tag{12}$$
と書き表される。更に(12)式の両辺に演算子 $\nabla$ を内積すると
$$\nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0} \tag{13}$$
となる。(13)式は渦無しの法則と呼ばれる式である。つまりスカラーポテンシャルで成すベクトル場 $\boldsymbol{F}$ では回転を誘発する渦が存在しないということである。
ならばこれとは別に発散を誘発する湧源が存在しないようなベクトル場 $\boldsymbol{F}$ も考えてみたいところだ。
つまり
$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0 \tag{14}$$
を満たすようなポテンシャルを定義できなかろうか。
そこで(14)式を満たすようにポテンシャルを
$$\nabla\times\boldsymbol{A}$$
と定義することにする。一般にスカラーポテンシャル $U$ と区別するためにこのポテンシャルはベクトルポテンシャルと言われている。
さて特にここで注釈を入れるべきなのかわからないようなしょうもないことではあるが、どこで入れるべきかもよく分からない。しかしかと言ってどこかのサイトや参考書では既知のものとして扱われるのでなあと思いつつ。いや単純なことで、ほぼ全てのサイトでは電位や静電ポテンシャルを $U$ に代えて $\phi$ と置いている。これは電圧に $V$ が使われているが、この $V$ と $U$ が紛らわしいという理由からであると考えるのが妥当であろう。本当かよと思われるかもしれないが手描きでは $U$ と $V$ の区別が付きにくいだけではなく、実際に昔の英語は $U$ と $V$ の区別がよく分かっていなかったそうである。
閑話休題ヘルムホルツの定理によれば
任意の3次元ベクトル $\boldsymbol{F}$ はスカラーポテンシャル $\phi$ とベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ によって
$$\boldsymbol{F}=-\nabla\phi+\nabla\times\boldsymbol{A}$$
を満たすものが存在する。
ヘルムホルツの定理
のようにベクトル場 $\boldsymbol{F}$ はスカラーポテンシャル $\phi$ とベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ を用いて書き表される。よって任意のベクトル場について、その発散、回転を取ると
$$\begin{cases}
\nabla\cdot\boldsymbol{F}=-\Delta\phi\\
\nabla\times\boldsymbol{F}=\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\nabla-\Delta\boldsymbol{A}
\end{cases}$$
のように湧源の項と回転の項に分離することができるのだ。
ここで少し前に遡って(13)、(14)式
$$\begin{cases}
\nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0} \\
\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0 \end{cases}$$
を満たすポテンシャルは実は一意に定まらず、ポテンシャルは任意定数 $C$ と任意スカラー関数 $χ$ を用いて
$$\begin{cases}
\boldsymbol{F}=-\nabla(\phi+C)\\
\boldsymbol{F}=\nabla\times(\boldsymbol{A}+\nabla χ)
\end{cases}$$
と表されるのである。これら $C,χ$ はどんな値でも良く、好きな値に変換することをゲージ変換と言う。
電磁ポテンシャルによる電磁場の記述
電磁場にもベクトルポテンシャルを導入してみよう。そこで磁束密度 $\boldsymbol{B}$ をベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ を用いて
$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A} \tag{15}$$
と置くと、明らかにマクスウェル方程式の第1式
$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0 \\$$
が成り立つ。
よって(15)式をマクスウェル方程式
$$\begin{cases}
\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0 \\
\nabla\times\boldsymbol{E}=-\dfrac{∂\boldsymbol{B}}{∂t} \\
\nabla\cdot\boldsymbol{D}=ρ \\
\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}+\dfrac{∂\boldsymbol{D}}{∂t} \\
\end{cases}$$
の第2式に代入すると
$$\begin{align*}
&\nabla\times\boldsymbol{E}=-\dfrac{∂\boldsymbol{B}}{∂t}\\
∴ &\nabla\times\boldsymbol{E}=-\dfrac{∂}{∂t}(\nabla\times\boldsymbol{A})\\
∴&\nabla\times\left(\boldsymbol{E}+\dfrac{∂\boldsymbol{A}}{∂t}\right)=0 \tag{16}
\end{align*}$$
となる。よって(16)式はスカラーポテンシャル $\phi$ を用いて
$$\boldsymbol{E}+\dfrac{∂\boldsymbol{A}}{∂t}=-\nabla\phi$$
となる。なんと! これにより動磁場による電場 $\boldsymbol{E}$ は電磁ポテンシャルを用いて
$$\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\dfrac{∂\boldsymbol{A}}{∂t} \tag{17}$$
と表されるではないか。
これにより動電磁場におけるガウスの法則は
$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-\Delta\phi-\dfrac{∂}{∂t}(\nabla\cdot\boldsymbol{A})=\dfrac{ρ}{ε_0}$$
となる。
ちょっと休憩
本記事は電磁ポテンシャルという考え方を紹介した。電磁ポテンシャルによってマクスウェル方程式等の諸原理を表現することで、どんな慣性系から観測してもマクスウェル方程式で書き表すことができるのだ。詳しくは次回以降紹介することになるが、その考え方から自然と特殊相対性理論へ誘導することが可能である。
初回(前回)
次回
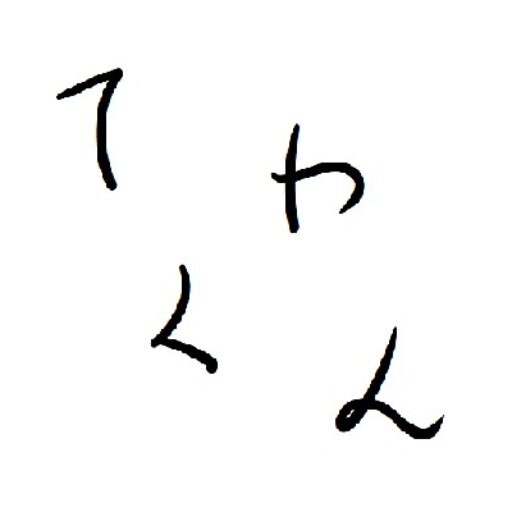
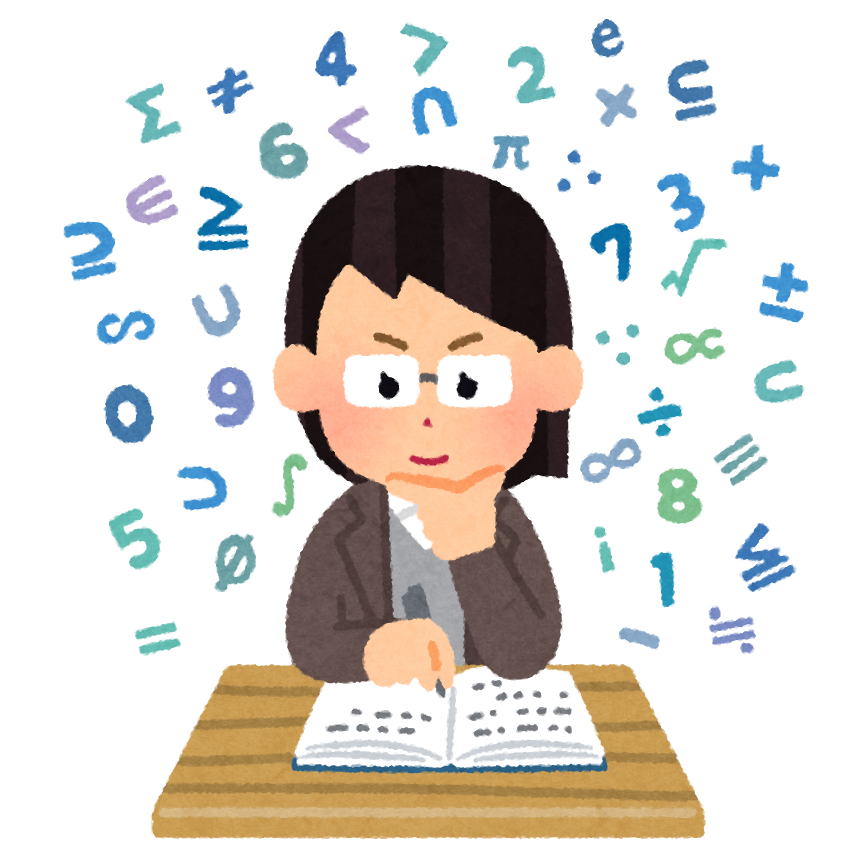
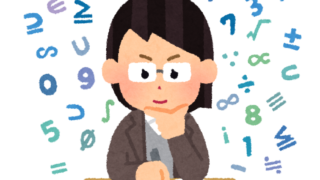
コメント