本記事はシリーズ「量子力学を学ぶために必要な基本的な考え方」の第3部となっています。第3部では量子力学特有の考え方である「不確定さ」について解説していきます。
初回
前回
次回
初めに
量子の不確定性とは、量子力学において同時に測定される2つの物理量の値が必ずしも互いに独立して確定するわけではなく、一方の物理量の値が決まればもう一方の物理量の値が確率的にしか決まらないことを示す概念です。
量子力学においては、観測が行われる前には粒子の位置や運動量などの物理量が確定した値を持つことはありません。代わりにこれらの物理量は確率的な値を持っており、測定を行うことでその値が確定することになります。例えばある粒子の位置を測定するとその粒子が存在する場所の確率分布を得ることができますが、測定を行う前にはその粒子の位置がどこにあるのかは確定していません。
量子の不確定性は位置と運動量のような一対の物理量に関して特に重要であり、これらの物理量は正準交換関係と呼ばれる非可換な関係を持っています。このため位置と運動量を同時に完全に決定することはできず、一方が確定するともう一方の値が不確定になります。この関係式は不確定性原理と呼ばれます。
不確定性原理は量子力学において非常に重要な概念であり、物理学や工学などの様々な分野で応用されています。例えば量子暗号通信や量子コンピュータの開発において不確定性原理が重要な役割を果たしています。
量子の不確定さ
交換子を用いた表現
古典力学では粒子は微分方程式を「解く」ことによってその運動を記述してきた。この微分方程式を「解く」ことで粒子の位置 $q_{(t)}$ やこれによって得られる運動量 $p_{(t)}$ の軌道を決定することができるのである。つまり古典力学において微分方程式が与えられているということは、ある時刻 $t_k$ の粒子をいつ観測してもこれらの挙動は既に確定されるということである。
後は微分方程式を解くことで正確な情報を知ることができる。例えば粒子に重力が働いているのなら微分方程式は
$$m\dfrac{d^2q}{dt^2}=-mg$$
となり、この微分方程式を解けばその粒子は上に凸の放物線を描くことが分かる。
このように微分方程式を解けさえしまえばもうその粒子の挙動は時刻 $t$ について決定されるのである。このような宇宙の全ての状態はそれ以前の状態から物理法則に従って必然的に変化し、決定されるという考え方は因果的決定論と呼ばれる。
よって位置 $q$ と運動量 $p$ の積は
$$qp=pq$$
のように可換である。何を当たり前のことを言っているんだと思われるのかもしれないが、そのように思えるということは私達の住む世界がそれだけ決定論的な事象に囲まれているからだ。
しかし量子論においてはむしろ決定論的な考え方には否定的である。実際に位置演算子を $\hat{q}=x$ と置き、運動量演算子を $\hat{p}=-i\hbar\dfrac{∂}{∂x}$ と置くと
$$\begin{align*}
\hat{p}(\hat{q}|\varphi\rangle)&=-i\hbar|\varphi\rangle+\hat{q}(\hat{p}|\varphi\rangle)\\
∴ (\hat{q}\hat{p}-\hat{p}\hat{q})|\varphi\rangle&=i\hbar|\varphi\rangle
\end{align*}$$
となる。よって位置演算子と運動量演算子の合成演算子 $\hat{q}\hat{p}$ は非可換であり、その差は $i\hbar$ となる。そこで交換子 $[\hat{q},\hat{p}]=\hat{q}\hat{p}-\hat{p}\hat{q}$ を用いて
$$[\hat{q},\hat{p}]=i\hbar\hat{I} \tag{10}$$
と置くことにする。(10)式は正準交換関係と呼ばれる。この式によれば位置と運動量を同時に定めることはできない(つまり同時に固有値を導出することはできない)ということである。逆に交換子について
$$[\hat{A},\hat{B}]=\boldsymbol{0} \tag{11}$$
となるときには2つの演算子 $\hat{A},\hat{B}$ による同時固有状態となっていることになり、更に2つの演算子 $\hat{A},\hat{B}$ によってそれぞれ固有ベクトル $|a_k\rangle,|b_k\rangle$ が対応する場合には、どちらの固有ベクトルでもあるような同時固有ベクトル $|a_k,b_k\rangle$ が存在するのだ。同時固有状態となっている場合には2つの物理量がいずれも確定している状態である。なお(11)式を満たすことと、同時固有状態であることは等価であるのだが、その証明は
$$\begin{align*}
\hat{A}\hat{B}|\varphi\rangle=\sum_k\varphi_k\hat{A}\hat{B}|a_k,b_k\rangle\\
\hat{B}\hat{A}|\varphi\rangle=\sum_k\varphi_k\hat{B}\hat{A}|a_k,b_k\rangle
\end{align*}$$
と
$$\begin{align*}
\langle i|\hat{A}\hat{B}|j\rangle=\sum_k\langle i|\hat{A}(|k\rangle \langle k|)\hat{B}|j\rangle\\
\langle i|\hat{B}\hat{A}|j\rangle=\sum_k\langle i|\hat{B}(|k\rangle \langle k|)\hat{A}|j\rangle
\end{align*}$$
がそれぞれ等しいことを利用して簡単に証明できる。具体的にこれらを計算することで
$$\begin{cases}
[\hat{A},\hat{B}]|\varphi\rangle=\boldsymbol{0}\\
(a_i-a_j^*)B_{ij}=0
\end{cases}$$
が得られる。上式は同時固有状態であることから可換であることを示し、下式は可換であることから $\hat{A},\hat{B}$ がいずれも固有状態になっていることを示している。
ここで具体的に(11)式 $[\hat{A},\hat{B}]=\boldsymbol{0}$ を満たす演算子とは $\hat{I}$ を単位行列として
$$\hat{A}=u\hat{B}+v\hat{I}$$
であり、また逆に(11)式 $[\hat{A},\hat{B}]=\boldsymbol{0}$ である場合にはこれを満たす $u,v$ が存在することが知られている。
不確定性原理
では位置 $x$ と運動量 $p$ はできるだけどれだけ定めることができるのだろうか。そこでそれぞれの演算子の標準偏差を
$$\begin{cases}
\Delta \hat{x}=\hat{x}-\langle\hat{x}\rangle\\
\Delta \hat{p}=\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle
\end{cases} \tag{12}$$
のように期待値を用いて書き表すことにする。なお位置演算子 $\hat{x}$ 及び運動量演算子 $\hat{p}$ はエルミート演算子であり、これらの標準偏差もエルミートとなる。
そこで
$$\begin{align*}
|(\Delta\hat{x}+iα\Delta\hat{p})\varphi|^2&=\langle\varphi(\Delta\hat{x}-iα\Delta\hat{p})|(\Delta\hat{x}+iα\Delta\hat{p})\varphi\rangle\\
&=\langle(\Delta\hat{x}-iα\Delta\hat{p})(\Delta\hat{x}+iα\Delta\hat{p})\rangle\\
&≥0
\end{align*} \tag{13}$$
と置いて計算してみると、
$$(13)=\langle\Delta\hat{a}^2\rangle+iα\langle\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}\rangle+α^2\langle\Delta\hat{p}^2\rangle≥0 \tag{14}$$
となる。これが成り立つためには(14)式の左辺について $α$ についての2次方程式
$$\langle\Delta\hat{a}^2\rangle+iα\langle\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}\rangle+α^2\langle\Delta\hat{p}^2\rangle=0$$
の判別式を $D$ と置くと
$$D=-\langle\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}\rangle^2-4\langle\Delta\hat{x}^2\rangle\langle\Delta\hat{p}^2\rangle≤0 \tag{15}$$
を満たさなければならない。また(14)式が実数になるためには $\langle\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}\rangle$ が純虚数か0になる必要があるから、(15)式は
$$\begin{align*}
4\langle\Delta\hat{x}^2\rangle\langle\Delta\hat{p}^2\rangle≥|\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}|\\
∴ \sqrt{\langle\Delta\hat{x}^2\rangle}\sqrt{\langle\Delta\hat{p}^2\rangle}=\Delta x\Delta p≥\left|\dfrac{\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}}{2}\right|
\end{align*}$$
となる。ここで
$$\begin{align*}
\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}-\Delta\hat{p}\Delta\hat{x}&=(\hat{x}-\langle\hat{x}\rangle)(\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle)-(\hat{p}-\langle\hat{p}\rangle)(\hat{x}-\langle\hat{x}\rangle)\\
&=\hat{x}\hat{p}-\hat{p}\hat{x}\\
&=[\hat{x},\hat{p}]=i\hbar
\end{align*}$$
であるから、結局(15)式は
$$\Delta x\Delta p≥\dfrac{\hbar}{2} \tag{16}$$
となる。この式から位置 $x$ と運動量 $p$ は同時に観測しようとすると、どんなに正確に計測しても測定誤差の積 $\Delta x\Delta p$ は最低でも $\dfrac{\hbar}{2}$ の不確定性が生じることが分かるのだ。
不確定性原理は何に応用されているのか
不確定性原理は量子力学以外にも波としての性質を持つものに対してなら元々備わっている特性である。例えば電磁波の学問としてある光学でも二重スリット実験による干渉縞ができる。これは光子が波としての性質を持つことから起こる実験である。光学的干渉計においては光の強度と位相を同時に正確に測定することはできず不確定性が生じるのである。
実は私達の生活にも「量子」の重要な性質である不確定性原理を利用している技術がある。例えば量子暗号通信においては不確定性原理を利用して情報を暗号化し、盗聴や傍受を防止することができる。量子暗号通信では通信の際に利用される光子の量子状態が盗聴や傍受によって変化するため、通信を盗聴する者は通信内容を完全に把握することができないのだ。
簡単な仕組みを紹介すると、量子暗号通信では通信の際に送信側がランダムな偏光状態を選び受信側がランダムな偏光軸を選択することで通信内容を暗号化するというものである。このとき不確定性原理によって偏光状態と偏光軸を同時に完全に決定することはできず、通信を盗聴する者が偏光状態を知ることはできても偏光軸を知ることができないため通信内容を復号することができなくなる。
もう一つ挙げるなら量子コンピュータである。これは不確定性原理を利用することで従来のコンピュータに比べて高速な計算を実現することができる。量子コンピュータは量子ビットと呼ばれる量子力学的に扱われる情報の基本単位を利用して計算を行う。不確定性原理によれば量子ビットは2つの状態(0または1)の重ね合わせ状態にあることができ、量子ビットの状態を測定することで重ね合わせ状態から0または1の状態に決定することができる。この不確定性原理を利用して、量子コンピュータは膨大な数の計算を同時に行い高速に処理を行うことができるほか、量子コンピュータは量子力学的な相互作用を利用して複雑な問題を解くことができるのである。
最後に
本記事でシリーズ「量子力学を学ぶために必要な基本的な考え方」は取り敢えずお仕舞いである。本シリーズを通して量子力学を学ぶために必要な基本的な考え方に触れてきた。このシリーズを読んで量子力学を代表するシュレディンガー方程式の意味や量子の
- 粒子と波動の二重性
- 確率的な解釈
- 不確定性
について簡単に紹介した。勿論これらは量子の性質のほんの一部にしか過ぎないのは言うまでもない。このシリーズは量子力学を初めて勉強する学生や勉強しているけど今一よく分からないような方向けに、量子の基本的な考え方を紹介したいという想いから書いたものである。このシリーズを呼んでくれた読者にはこれを機に量子力学の学習を進めてくれると大変嬉しい。
初回
前回
次回
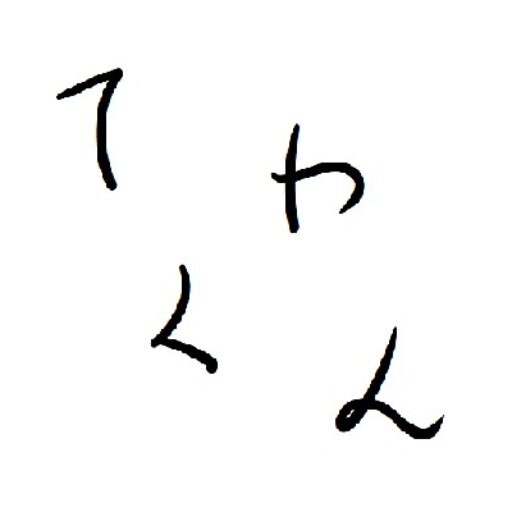
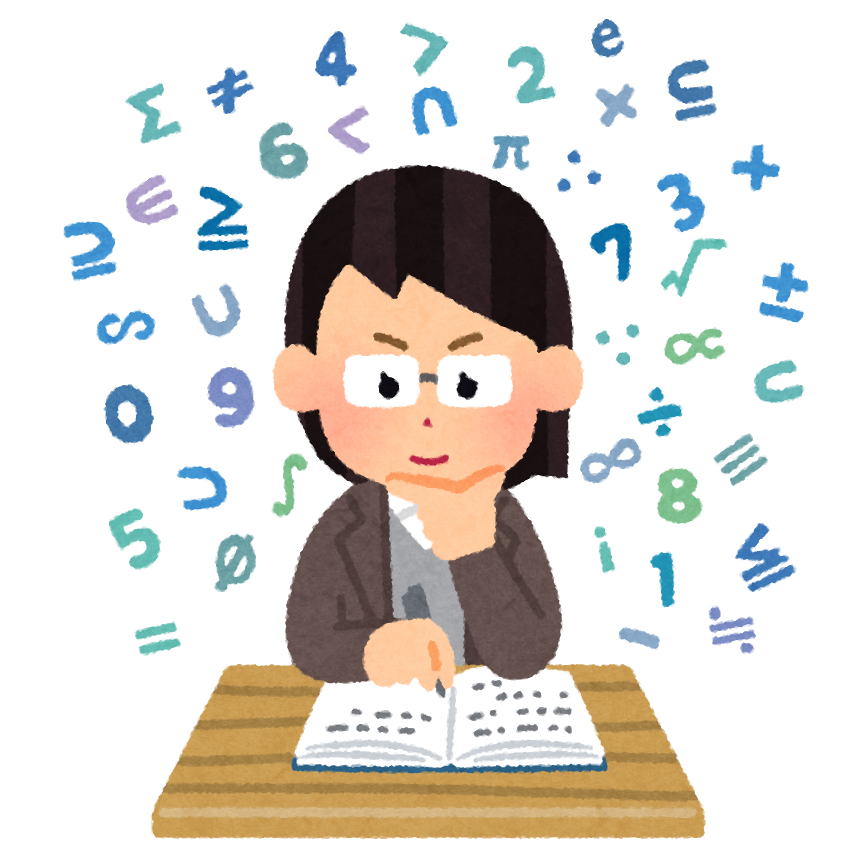
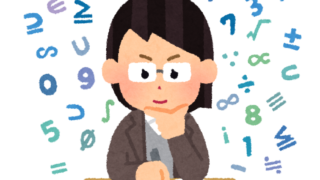
コメント