本記事はシリーズ「量子力学を学ぶために必要な基本的な考え方」の第2部となっています。前回ではシュレディンガー方程式について解説しましたが、今回はこれを用いて幾つか調べていきます。
初回(前回)
次回
初めに
量子力学における状態ベクトル $|\varphi\rangle$ とは物理系がとりうる状態の全体を表すベクトルです。状態ベクトル $|\varphi\rangle$ は内積や外積といったベクトル演算を通じて他の状態ベクトルとの関係を表現できます。
また量子力学において状態ベクトル $|\varphi\rangle $ とは、観測を行うことで物理系がとりうる値を確率的に予測することができる確率密度関数として解釈できます。
ハミルトン演算子 $\hat{H}$ とは量子力学におけるエネルギーを表す演算子です。具体的には$\hat{H}$ を物理系の状態ベクトル $|\varphi\rangle$ に作用させることで、物理系が持つエネルギーを計算することができます。これによって物理系の状態が時間とともにどのように変化するかを予測することができます。
波動関数 $|\varphi\rangle$ とハミルトン演算子 $\hat{H}$ を詳しく見る
確率密度関数という視点から見る波動関数 $\boldsymbol{\varphi}$
ブラ-ケット記法によれば波動関数 $|\varphi\rangle$ が規格化されているということは
$$\langle\varphi|\varphi\rangle=1$$
であるということである。これを積分を用いて表現すると
$$\begin{align*}
\int_V\boldsymbol{\varphi}^*\boldsymbol{\varphi}d^3r&=1\\
∴ \int_V|\boldsymbol{\varphi}|^2d^3r&=1
\end{align*}\tag{6}$$
となる。これは正しく統計学における確率密度関数 $ρ=|\boldsymbol{\varphi}|^2$ の積分であり、全事象を積分することで総確率1が求まる。つまり当たり前のことではあるが、全領域を調べれば全粒子が存在するということである。
では時間変化した場合には粒子の存在確率はどのように変化するのだろうか。
ここではこの議論のために、シュレディンガー方程式(5.1)式とこれの複素共役の時間微分により
$$\begin{cases}
\dfrac{∂\boldsymbol{\varphi}}{∂t}=\dfrac{1}{i\hbar}\left(\dfrac{-ih}{2m}\Delta+V_{(\boldsymbol{r})}\right)\boldsymbol{\varphi}\\
\dfrac{∂\boldsymbol{\varphi}^*}{∂t}=-\dfrac{1}{i\hbar}\left(\dfrac{ih}{2m}\Delta+V_{(\boldsymbol{r})}\right)\boldsymbol{\varphi}^*
\end{cases}$$
を用いる(ポテンシャル $V_{(\boldsymbol{r})}$ は実ポテンシャルとする)。
よって(6)式の時間変化は
$$\begin{align*}
(左辺)&=\dfrac{∂}{∂t}\int_V\boldsymbol{\varphi}^*\boldsymbol{\varphi}d^3r\\
&=\int_V\dfrac{\boldsymbol{\varphi}^*}{∂t}\boldsymbol{\varphi}+\boldsymbol{\varphi}^*\dfrac{∂\boldsymbol{\varphi}}{∂t}d^3r\\
&=\int_V\dfrac{\hbar}{2mi}\left((\Delta\boldsymbol{\varphi}^*)\boldsymbol{\varphi}-\boldsymbol{\varphi}^*(\Delta\boldsymbol{\varphi})\right)d^3r\\
&=-\int_V\dfrac{\hbar}{2mi}\nabla\cdot\left(\boldsymbol{\varphi}^*(\nabla\boldsymbol{\varphi})-(\nabla\boldsymbol{\varphi}^*)\boldsymbol{\varphi}\right)d^3r\\
\end{align*}$$
となる。
しかし一般的には確率流束(密度)を
$$\boldsymbol{J}=\dfrac{\hbar}{2mi}\left(\boldsymbol{\varphi}^*(\nabla\boldsymbol{\varphi})-(\nabla\boldsymbol{\varphi}^*)\boldsymbol{\varphi}\right)$$
と定義しているので本記事もそれに倣って定義しよう。
このとき結局(6)式の時間変化から
$$\begin{align*}
\dfrac{∂}{∂t}\int_Vρd^3r&=-\int_V\nabla\cdot\boldsymbol{J}d^3r\\
∴ \dfrac{∂ρ}{∂t}&=-\nabla\cdot\boldsymbol{J}
\end{align*}$$
と書き表される。よって確率について連続の方程式
$$\dfrac{∂ρ}{∂t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$$
が得られる。
量子力学において連続の方程式は確率保存則を示す。
ハミルトン演算子 $\hat{H}$ を解剖する
時間依存しないシュレディンガー方程式は固有方程式(4)式
$$\hat{H}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle=E|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle \tag{4}$$
で表現される。 (4)式の両辺に左からブラ $\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|$ の内積を取ると
$$\begin{align*}
\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|\hat{H}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle&=\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|E|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle \tag{4}\\
&=E\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle
\end{align*}$$
となる。ここで波動関数 $|\varphi\rangle$ が規格化されている場合には
$$\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|\hat{H}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle=E \tag{7}$$
を得る。この式が意味するところは $\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|\hat{H}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle$ を計算するとエネルギー $E$ が得られるということである。
ここでハミルトン演算子 $\hat{H}$ とはエネルギー固有値 $E$ を得るための演算子である。つまり実際に可視化される(言い換えれば確定した)エネルギーは不確定なエルミート演算子 $\hat{H}$ による波動関数 $|\varphi\rangle$ の線型変換によって得られる。ここで言う得られるエネルギー $E$ とは正しくハミルトン演算子 $\hat{H}$ の期待値であろう。このエネルギー $E$ について詳しく見ていく。
固有空間におけるエネルギー $E$
固有方程式で得られたエネルギー $E$ とはそれぞれの固有値 $E_k$ に対応し、波動関数 $|\varphi\rangle$ は全ての固有ベクトル $|E_k\rangle$ の線型結合
$$|\varphi\rangle=\sum_k\varphi_{(E_k)}|E_k\rangle \tag{8}$$
で表される。
本記事ではこのように全ての固有ベクトル $|E_k\rangle$ によって波動関数を表現する場合には $|\varphi\rangle$ を状態ベクトルとし、 $\varphi_{(E_k)}$ を波動関数とする。しかし文献によっては波動関数と状態ベクトルを混合していたり、本記事でも固有ベクトルについて深く触れる前には敢えて状態ベクトルという言葉を避けていたりしているので注意されたい。
今は離散的ではあるが、基底に位置を表す演算子 $\hat{x}$ による固有ベクトル、つまり位置を定める状態の全体 $|r\rangle$ による線型結合で表現するとき、位置は連続であるなら
$$|\varphi\rangle=\int_V\varphi_{(\boldsymbol{r})}|r\rangle d^3r$$
のように書き表される。
固有エネルギー $E$ で表現される(8)式について、固有ベクトル $|E_k\rangle$ が完全正規直交系を成すので(8)式に左からブラ $\langle E_k|$ の内積を取ると、
$$\langle E_k|\varphi\rangle=\varphi_{(E_k)}$$
のようにある固有ベクトル $|E_k\rangle$ における展開係数 $\varphi_{(E_k)}$ が得られる。
よって観測値が実数であるのならハミルトン演算子 $\hat{H}$ はエルミート演算子であることが分かる。なぜだと思ったら以下の記事
の『内積への挿入に適した演算子はどれか』を読もう。
そのためエネルギー固有値 $E_k$ におけるハミルトン演算子は固有ベクトル $|E_k\rangle$ を用いて
$$\hat{H}_k=|E_k\rangle\langle E_k|$$
と置くと、
$$\begin{align*}
\langle\varphi|\hat{H}_k|\varphi\rangle&=\langle\varphi|E_k\rangle\langle E_k|\varphi\rangle\\
&=|\langle E_k|\varphi\rangle|^2\\
&=|\varphi_{(E_k)}|^2 \tag{9}
\end{align*}$$
となる。ただし $\hat{H}_k$ は「 $\hat{H}$ の固有値 $E_k$ に属する固有空間への射影演算子」と呼ばれる。
射影演算子については以下の記事で解説している。射影演算子を幾何学的な観点から解説している
(9)式はエネルギー固有値 $E_k$ による波動関数 $\varphi_{(E_k)}$ の大きさの2乗となっていることから、波動関数 $\varphi_{(E_k)}$ はエネルギー固有値 $E_k$ が得られる確率振幅と解釈することができる。
つまり(7)式で得られるエネルギー
$$\langle\varphi_{(\boldsymbol{r})}|\hat{H}|\varphi_{(\boldsymbol{r})}\rangle=E \tag{7}$$
について、どれを測定するのか不確かながらも確実にどのエネルギー固有値 $E_k$ かは測定することになるのだ。
従って(9)式で得られる結果とは、エルミート演算子 $\hat{H}$ によって得られる測定値 $E_k$ の頻度と言えよう。そのため(7)式で得られるエネルギーとはエルミート演算子 $\hat{H}$ の期待値 $\langle\varphi|\hat{H}|\varphi\rangle=\langle \hat{H}\rangle$ と見なすことができる。
このように物理量を観測したときにある値が得られる確率を与える法則はボルンの規則と言われている。
縮退がある場合
今まではエネルギー固有値 $E_k$ に対して1つの固有ベクトル $\langle E_k|\varphi\rangle$ が対応していた。つまりある固有値 $E_k$ に属する固有空間が1次元のものであるとしていた。ここでは1つのエネルギー固有値に対して固有空間が多次元である場合を考える。
エネルギー固有値 $E_k$ に $m$ 個の固有ベクトル $|E_k,1\rangle,|E_k,2\rangle,\cdots,|E_k,m\rangle$ が対応しているとき、「固有値 $E_k$ に $m$ 重の縮退がある」等と言う。このとき固有値 $E_k$ の射影演算子 $\hat{H}_k$ を
$$\hat{H}_k=|E_k,1\rangle\langle E_k,1|+|E_k,2\rangle\langle E_k,2|+\cdots+|E_k,m\rangle\langle E_k,m|$$
と置くことで縮退が無い場合と同じようにボルンの規則を使うことができる。実際
$$\begin{align*}
\langle\varphi|\hat{H}_k|\varphi\rangle&=\langle\varphi|(|E_k,1\rangle\langle E_k,1|+|E_k,2\rangle\langle E_k,2|+\cdots+|E_k,m\rangle\langle E_k,m|)|\varphi\rangle\\
&=|\langle E_k,1|\varphi\rangle|^2+|\langle E_k,2|\varphi\rangle|^2+\cdots+|\langle E_k,m|\varphi\rangle|^2\\
&=|\varphi_{(E_k)}|^2
\end{align*}$$
のように測定値 $E_k$ が得られる確率を計算することができるのだ。
ちょっと休憩
本記事ではシュレディンガー方程式で使われるハミルトン演算子 $\hat{H}$ や波動関数 $\varphi$ 、状態ベクトル $|\varphi\rangle$ の性質について解説してきた。その中で量子の持つ波動性には確率の考え方ができ、それにより量子を確率的な観点から解釈できることを紹介した。次回では量子の不確定さを調べていく。
初回(前回)
次回
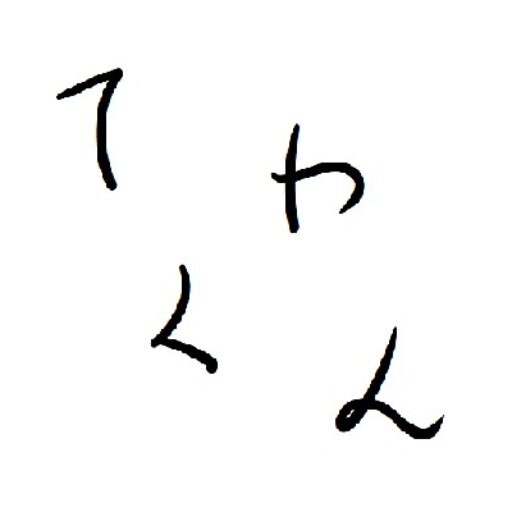
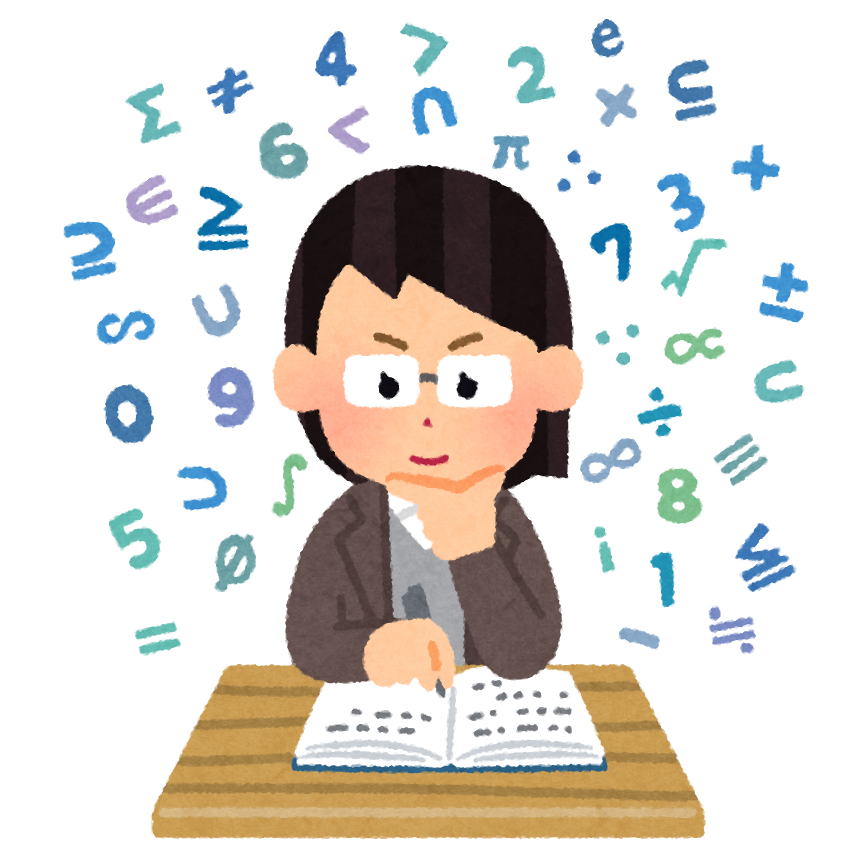
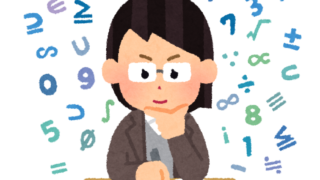
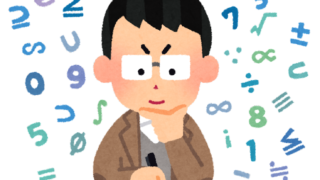
コメント